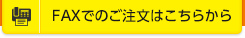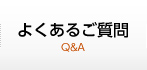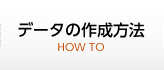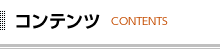世説人語
大学ランキング2024が出揃えました。
世界三大大学ランキングの2024年版が出揃えました。
一、イギリスの教育コンサルディング会社Quacquarelli symond が毎年6月に公表する「Quacquarelli symond QS World Uniwersity Rankings」で、略称は(QS)です。
二、イギリスの高等教育情報誌 The Time Higher Education が出している「The Time Higher Education World University Ranking」で、略称 (The)です。
三、アメリカの U.S. News & World Report 社が発表する「U.S. News Releases Best Global Universities Ranking」で、略称(U.S.News) です。
上記の三つはいずれも教育と研究の質、学校の国際性と産業への貢献度をバランスよく評価の基準にしているので、代表的な世界大学ランキングになっています。日本と違い、海外では夏受験、9月から新学期の始まる学校が多く、国内に拘らず、グローバルの時代に世界を羽ばたく人材として、海外の大学も視野に入れている学生や保護者が学校の選定のご参考になればと思います。
この三つ以外も大学学術ランキング「Academic Ranking of World Universities」が有名で、略称(ARWU)です。主に大学研究者らが「ネイチャー」誌と「サイエンス」誌など自然科学研究分野で発表する論文の数及び論文の被引用数などを統計の重点が置かれているので、今回は割愛します。
三つの異なるランキングを比較しやすいように50位までの一覧表にまとめました。
近年、アジアの大学の飛躍も目覚ましく、日本の東京大学、京都大学の地位は健在ですが、韓国のソール大学も依然レベルが高いです。特にシンガポール、香港及び中国本土の大学は多数上位50、上位100にランクインされています。シンガポールの両雄、シンガポール国立大学と南洋理工大学は世界大学の10位前後に認められるようになりますし、中国香港の名門、香港大学と香港中文大学も上位に食い込んできています。中国北京の北京大学と精華大学、上海の復旦大学と交通大学も順位の進化を成し遂げています。
アジアの経済発展が大学の教育と研究のレベルアップをもたらしていると同時に、大学で育った人材も更なる技術革新と経済発展を支えていく好循環になっているのではないかと思います。21世紀はアジアの世紀と言われていますが、アジアの世紀を実現するため、教育と研究レベルの躍進が不可欠です。アジア、頑れ!!!
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
EV自動車進出の新たな舞台・・・下巻
2023年にはタイで購入する電気自動車の総台数は国内販売の約9%を占めると伝えられています。中国の新エネルギー車ブランドがタイ市場に参入して以来、ここ数年でブランドや品質に対する認知度が急速に向上し、市場価格も魅力的で、販売が進んでいると評価されています。
100万バーツ以内で購入できる新エネルギ車が増え、アフターサービス体制も充実しているため、タイの消費者の購買意欲も徐々に高まっているそうです。 これは新エネルギー車の促進と地元産チェーンの発展を目指すタイ政府の戦略計画に関連していますが、日本が50年間をかけて、タイで培った自動車進出のノウハウや市場戦略、またかつてほぼ独占していたタイを生産基盤としての東南アジア市場への輸出、これからどうなっていくのでしょうか。タイの自動車市場のパターンが大きく変わろうとしています。それに連動して、活気ある東南アジアの自動車市場も動き出していくと予想されています。
データによると、2023年にはタイ市場における中国車のシェアが約5%から約11%に急増する一方、日本車のシェアは約90%から78%に低下しました。中国ブランドは純粋な電気自動車市場の約80%を掌握し、タイの電気自動車市場の主導的なトレンドを引き起こしています。
関連業界団体によると、タイの電気自動車の購入は2023年に比べ、2024年末までに倍増すると予想されている。タイにおける中国車の進出に大きな意義を齎しています。タイは東南アジア最大の自動車製造・輸出国であり、東南アジアで最も活発な電気自動車市場を有し、世界で10位の自動車生産国でもあります。タイでの徹底的な展開を通じて、自動車メーカーは東南アジア諸国と世界の右ハンドル市場にさらに効果的に影響を与えるでしょう。
ラッキープリントスタッフ一同
EV自動車進出の新たな舞台・・・上巻
第45回バンコク国際モーターショーが3月27日に開幕しました。今回のショーには、欧州、日本など世界の主要自動車メーカーのほか、中国、インド、ベトナム新興国のブランドも参加し、EV車も含めて、多くのメーカーが新型モデルも発表しています。
4月7日まで開催しますが、ロイター通信は3月25日に今週のバンコク国際モーターショーでは中国の自動車メーカーが「注目の的」になると報じ、長年タイの自動車市場を支配してきた日本の自動車大手はますます厳しい課題に直面していると述べました。
最近、バンコクの街で中国の自動車ブランドが目につくようになり、中国の新エネルギタクシーも多くなっています。中国自動車ブランドはタイを中心とした東南アジアの自動車市場への進出を続けており、特に新エネルギー車が勢いを増している。統計によると、2023年のタイにおける純電気自動車の新車登録台数は7万6,000台を超え、2022年の9,678台から大幅に増加した。そのうち、中国ブランド車は新エネルギー車市場の80%を占める。タイの純電気自動車販売台数トップ10には、合計8台の中国車がランクインしており、上位3台はすべて中国車ブランドとなっている。
タイは昨年2027年までに電気自動車を購入する消費者に1台当たり最大10万バーツの補助金を支給する(約416,300円)と発表しました。 2030年にタイの自動車生産の30%を電気自動車が占めるという目標を達成するため、タイ政府は2024年から2025年まで資格のある外国自動車メーカーに対し、自動車輸入税と消費税を減免しますが、タイでの現地生産を義務付けます。
タイ政府が新エネルギ車、特に電気自動車は省エネの循環型社会を目指しながら、自国一大基幹産業として育てる思惑があります。それは中国自動車メーカーの海外進出の意欲と合致しています。 2023年にはBYD、奇瑞汽車、広汽恵安、長安汽車などの中国自動車メーカーがタイに純電気自動車の生産工場を設立する計画を相次いで発表しており、長城汽車、上海汽車グループなども工場予定地を選定してきました。
ラッキープリントスタッフ一同
「初芝」の夢と「東芝」の現実・・・その五(終)
米国の制裁などでどん底に陥った東芝はようやく回復してきたところ、脆弱な財務基盤のまま、2006年に同じ原子炉メーカーの大手のアメリカのウエスチングハウス(Westinghouse,略称WH)を評価額の三倍の6216億円に吊り上げられた金額で、77%の株を入手しました。欧米の電力自由化を契機に原発事業の海外進出を目論んでいました。
2年後の2008年、米国発の金融危機を世界の経済に大きな打撃を与えました。もっと原発事業に決定的なパンチを食らわせたのが2011年の東北地震でした。地震後、福島の原子炉が爆発し、核漏れ事故が発生しました。世界中で脱原発の機運が高まって、海外進出を考えた東芝も原発計画を放置せざるを得ませんでした。
2015年に財務困難に陥った東芝が粉飾決算を摘発されました。更に2020年のコロナパンディミックが東芝を窮地にお追い込まれました。
ついに一週間前の12月20日に東芝は上場廃止され、東証株式市場から姿を消しました。
東芝が再生への”茨の道”がつつきますが、果たして返り咲きができるのでしょうか。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
「初芝」の夢と「東芝」の現実・・・その四
アメリカ合衆国の安全を脅かしたとして、通商法301条(貿易相手国の不公正な取引に対して協議、問題が解決しない場合は制裁)の発動をほのめかしました。米国が「日本メーカーの不当廉売によって、急速的にシエアを拡大しているのに自国の市場は閉鎖的である」と出張し、日本の市場開放及び半導体メーカーの特許開放を迫りました。尋常でない米政府の圧力を感じ、時の日本政府がやむを得ず米国と「日米半導体協定」を結びました。
それにも関わらず、1987年4月にダンピング(不当廉売)が続いていることを理由に、日本に制裁を行いました。日本製の半導体を含んで、パソコン、カラーテレビなどの電気製品に対して100%の関税率を一方的に課すことになり、総額3億ドルの関税を引き上げました。
1987年6月30日に米国連邦議会堂前でアメリカ議員らが交互にハンマーで東芝製ラジカセを叩いている写真は象徴されるように半導体シエア2位の東芝に対し、「東芝制裁法案」を議会通過し、数年間の東芝製品の米国輸入を禁じました。余談ですが、30年後の2019年、アメリカは再びこのハンマーを高く挙げ、降ろしている先に今度は中国のファーウェイ(華為技術有限会社)という通信機器・インフラを開発製造メーカーがあります。貿易不均衡の是正や国家安全のためと理由を付けていますが、出た杭を打つという構図は30年前と変わりません。
対日制裁発動後、69歳の中曽根総理大臣は日米の緊張を緩和するため、米国に赴き謝らなければなりませんでした。後に東芝の工作機械事業部の部長らを日本警察に逮捕され、東芝の会長、社長も辞職に追い込まれました。調査という名目で、多くの内部技術資料も米国に渡ったと伝えられています。
ノルウェーの調査により、1980年代にノルウェー、フランス、イタリアも同様な先端工作機械をソ連に販売しましたが、米国に猛烈な追究されたのは東芝だけでした。恐らく、80年代の日本は半導体や電気製品のほか、車のシェアも伸びていて、対米黒字がどんどん膨らんいるからのが大きな理由ではないでしょうか。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
「初芝」の夢と「東芝」の現実・・・その三
2日前にアルゼンチンの新大統領は自国通貨のペソが米ドルに対し、50%を切り下げと宣言しました。ドルベースで単純計算すると、アルゼンチンの通貨の価値は50%低下することになり、購買力も半減しました。それと対照的にプラザ合意後の円の価値が一気に高まりました。宝くじに当たったように持ち金の購買力が大幅に伸びましたので、多くの富裕国民や企業は米国の高級住宅や高級ホテル、ゴルフ場を買い占めました。1989年に三菱地所があのマンハッタンの5番街に位置するロックフェラーセンターを買収したのは、「ジャパンマネー」が海外資産を買いあさりの象徴とも言えます。
しかし、「合意」とは言え、米国が自らの利益のため、意図的な為替レート操作によって急進的な通貨変動は80年後半の日本繁栄を齎しましたが、あくまでも通貨高騰による株式や不動産バブルの虚像に過ぎなかったことは90年代に入って分かりました。
振り返れば1985年の「プラザ合意」は日本経済が成長から停滞へと大きな転換を迎えた年だと思います。東芝にとっても1985年は盛衰興亡の分水嶺と言えます。
東西冷戦の時代に西側が共産圏の国々に対して、軍事技術と戦略物質の輸出を規制するため、COCOM(ココム)という「多国間輸出統制調整委員会」が設置し、本部はパリに置かれ、日本もそのメンバーです。
しかし東芝は先端な工作機械の輸出禁止を知りながら、伊藤忠商事などを経由し、2軸制御の大型旋盤と虚偽な許可申請を通産省に出しました。実際に9軸制御可能な高性能モデルの本体8台をソビエト連邦に輸出しました。よってソビエトの原子力潜水艦の製造技術及び静粛性を大幅に向上し、アメリカ海軍が対ソ連原潜の探索優位性を失いました。1982~1984年にかけて、35億円の高値を付けて、ノルウェー経由での輸出でした。後に内部告発のため、発覚されました。米国が日系企業叩きに絶好の口実を与えました。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
「初芝」の夢と「東芝」の現実・・・その二
では、一国の代表的な大企業の衰退は時代の流れや経営方針の判断ミスなどいろいろな要因があります。しかし、「ローマは一日にして成らず」、その結果を招いた経過を検証することで、いくら小さいな企業でも戒めとして、意義のあることだとは思います。
20世紀の80年代、日本の半導体技術と性能が飛躍的な進歩を成し遂げ、本場のアメリカを超え、ICチップの最大供給先になりました。日本企業の半導体チップは欧米製の同類半導体の製品と比べれば、品質は全く劣らず、価格は常に10%安く設定していたため、欧米メーカーがどうしても日系企業との競争に勝てませんでした。その代表の日系企業はまさに「東芝」と「日立」でした。よってアメリカの対日貿易赤字が膨らみに膨らんで、米国内に「安くて品質が良い」と日系電機製品への賛美をしながら、一方「狼が来た」とアメリカ産業界が日本メーカーへの敵視も齎しました。
当時のアメリカの起業家が電気半導体分野で日系企業と競争し、日本市場、若しくは日系企業の目的市場に進出しようとすると、投資ファンドからの融資は不可能と言われて、日系企業に勝つというのは無謀だからです。
1983年、アメリカ商務部の調査報告では、米国は飛行機製造、宇宙航空開発の分野を除いて、半導体技術、光ファイバー、電気制御機械技術等の分野において日本に全面的に遅れたと指摘しました。1985年に世界の半導体製造メーカーのトップ10に半数は日本企業となっていました。
その後、アメリカがイギリス、フランス、ドイツと日本の代表をニューヨークのプラザホテルに招集し、現代歴史の本にも出てくる「プラザ合意」を結びました。イギリスポンド、フランスフラン、ドイツマルク、日本円などの世界主要通貨に対して、大幅なドル安を容認しました。米国の製品輸出の促進と貿易赤字の解消が目的でした。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
「初芝」の夢と「東芝」の現実・・・その一
76歳になった「島耕作」がついに副知事に就任したという「ニュース」を見ました。佐賀県の副知事らしいですが、もちろん、現実社会のリアルな話ではなく、弘兼兼史さんが描いて、講談社が出版しているマンガシリーズ「島耕作」の中の出来事でした。
大企業で働く男たちが描かれている物語で、主人公の課長「島耕作」も企業と共に日本の高度成長期に合わせて出世していきます。オフィスラブから、社内派閥抗争や企業間競争、アジア進出など時代と共に企業の歩みと人間のドラマを40年間も渡って演じ続けています。
恐らく、作家の弘兼さんは松下電機産業で三年間の勤務をしたから、数々の若者が憧れる大手電機メーカーを舞台にすることができました。マンガの中に「初芝」という日本を代表する大手電機企業を架空していますが、作者の経歴を知らない読む側からすれば、原型の松下電器より、どうも現実の大企業「東芝」を母体にしているのではないかと思います。
1875年創立で、家電、電気事業、半導体、エネルギなど多岐にわたって、150年間発展してきた日本有数の基幹企業の一つです。嘗て大手重電三社(日立製作所、東芝、三菱電機)と呼ばれる一角になり、電球、洗濯機、冷蔵庫、掃除機、炊飯器、電子レンジ、ノートブックパソコンなど、国産第一号の家電製品を次から次へと発売しきした。省エネ、自然に優しい白物家電分野において、今風で言うとSDGsの草分け的な存在でもありますが、2015年の粉飾決算が発覚され、経営不振に陥ていることは周知の通りだと思いますが、経営を立て直すため、主力事業の白物家電を中国大手メーカー(美的グループ)に売却し、医療機器事業をキャノンの手へ、半導体メモリー事業を米韓企業連合に2.3兆円で渡しました。
今年に入り、経営の安定化を目的に、海外ファンドを排除したうえ、国内投資ファンドの日本産業パートナーズが提案した条件(非上場化)を受け入れ、全体の80%近くにのぼる株式の公開買い付けを合意しました。
年内12月20日にあの名門、東芝の上場廃止が東京証券取引所から宣告されることになり、残念ながら「東芝」の凋落が決定的になる一日に間違いがありません。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
風車に立ち向かうか?(下)
その気球騒動による米中の外交合戦がおさまらないうち、次も中国の偵察気球ではないかとまたも不明飛行体を3つ撃墜しました。分析した結果、今回はどうやら中国と無縁らしい。しかも2月11日にアラスカ上空で浮遊している不明飛行物に対し、まずF35戦闘機を飛ばしました。飛行体を偵察確認し、まわりの空港も交通管制を行いました。その後、F22が2機出撃し、13000mの高度で血税5280万円のミサイルを2発発射して撃墜しました。
しかしその後、米国のアマチュア気球団体が自分たちが飛ばした気球はアラスカの上空で行方不明となっていることを明らかにしました。なんという皮肉な事態でしょう。中国を撃破するどころかオウンゴールをしました。
それは恐らく世界の王者が自信を失いつつ、力んで招いた空振りだと思います。中学校時代に読んだスペイン作家セルバンテスの小説「ドン・キホーテ」の中の一節を思い出しました。「中世騎士の夢を抱いていたドン・キホーテが3~40基の風車に出くわしたところ、それを巨人と錯覚し、全力で勇敢に向かい打ちましたが、風車に衝突した結果、跳ね返されて野原に転がりました。」と・・・
今回の出来事は、米国の世論風潮で政治家や軍事専門家や有識者の話よりも、物事を科学的且つ常識的に考えれば、もし本当に中国の偵察気球であれば、意図的に米国の軍事施設を偵察するなら、30000~40000mの高度を維持し、太平洋を横断できたこと、しかも所定の米国核施設3箇所をそれぞれ正確に通るようにその制御技術は世界一に違いありません。
また、中国側がそのように気球の制御を精密にできれば、常にミサイル攻撃を回避できる30000~40000mの高度を保てば、F22もその高度に成すすべなく、撃墜も免れるのではないでしょうか。
中国側が米国の撃墜に協力をし、超精密制御で18000mまで高度を下げてくれた可能性があるのだろうか、それを除けば、やはり「偏西風の影響を受けてコースから外れてしまった」という中国側の発表が、米国の疑心暗鬼より信憑性があるのではと思います。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
風車に立ち向かうか?(中)
1960年、メーデーの日(5月1日)に東西冷戦の真っ只中、ソ連を高空偵察飛行していたアメリカの偵察機、ロッキードU2が旧ソ連に撃墜され、他国への領土侵犯と偵察の実態が発覚したにも関わらず、米国が否認をしました。ソ連側は逮捕したパイロットと撃墜したU2の残骸を世界に公表した後、米国がやむを得ず、偵察の事実を認めました。恐らく人類史上において、地対空ミサイルを用いて飛行体を打ち落とした最初の試みだと思います。また、その事件によってフランスのパリで予定されていた米ソ首脳会談も中止されました。
1962年9月、台湾が米国製の高空偵察機U2で20000m以上の上空で中国北西の核爆弾発射現場を覗き見、中国に撃墜されたのと同じように、当時20000mの上空を飛べる戦闘機がなく、外国の記者に「どういう秘密兵器で撃ち落としたのでしょうか」という質問に対し、中国の外務省が「竹竿で突き落としました。」と秘密厳守すべき、ジョークを飛ばしたことを思い出します。近年の情報解禁で、旧ソ連の協力で、地対空ミサイルを配備した中国空軍が実戦で米国製の偵察機を撃墜したそうです。あれから60年ほど経った今、人の国の主権や領空を常に無視し、偵察の常習犯であるアメリカが逆に他国の高空気球に「偵察」されたこと、もしこれは中国側が意図的に行ったのなら、少なくとも欧米列強が発展途上国の立場や利益を顧みず、利己主義的な世界主導という「覇権力」はもはや揺るぎないものではないと見ていいと思います。
今回、回収された気球の残骸をFBIに渡し、解析を行った結果、気象観察用の装置とそれほど変わらないですが、「偵察」かただの気象「観察」か、見た目一文字だけの違いになりますが、目的も判明できないまま、次の世論操作に乗り出しました。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同