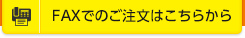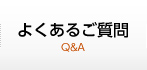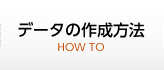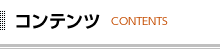世説人語
アジア大学ランキング
大学ランキングはいくつかありますが、ロンドンにある高等教育の評価機構QS(Quacquarelli Symonds)社が公表するランキングは大学ごとに「専門家からの評価」、「学生一人あたりの教員数」、「国際化指数(外国人教員、留学生の比率)」、「教員の論文被引用率」の4分野、各25%の評価基準で、総合得点を算出します。比較的に客観的なランキングとして、知られています。
近年、QS World University Rankings(QS世界大学ランキング)のほか、発展が著しいアジアに注目し、アジア名門大学ランキングを公表するようになりました。
2020年版のランキングを見てみると 1位「シンガポール国立大学(NUS)」、2位「南洋理工大学(NTU シンガポール)」、3位「香港大学(中国香港)」、4位「精華大学(中国北京)」、5位「北京大学(中国北京)」、6位「浙江大学(中国浙江省)」、7位、「復旦大学(中国上海)」、8位「香港科学技術大学(中国香港)」、9位「韓国科学技術院(KAIST韓国)」、10位「香港中文大学(中国香港)」と日本の大学の存在感が薄くなっていることが分かります。
同機構10年前の2010年版のランキングを調べました。以下のようになっていました。1位「香港大学」、2位「香港科学技術大学」、3位「シンガポール国立大学」、4位「香港中文大学」、5位「東京大学」、6位「ソウル大学」、7位「大阪大学」、8位「京都大学」、9位「東北大学」、10位「名古屋大学」と前10位の内に日本の大学が半分を占めました。それと対照的に中国の大学は香港のを除けば、1つも入っていませんでした。12位の「北京大学」と16位の「精華大学」は中国大陸において、もっとも上位の大学になっていました。
また、イギリスの高等教育専門誌「The time Higher Education」もアジア大学ランキング2020(Asia University Rankings 2020)を今年の6月に公表しました。所謂タイムズアジア大学ランキングです。総合ランキングは 1位「精華大学」、2位「北京大学」、3位「シンガポール国立大学」、4位「香港大学」、5位「香港科学技術大学」、6位「南洋理工大学」、7位「東京大学」、8位「香港中文大学」、9位「ソウル大学」、10位「中国科学技術大学(中国安徽省)」&「成均館大学(SKKU 韓国)」となっています。トップ2は中国の大学で、全10位の中に香港の3校も含めれば、中国が60%を占めることになります。
ランキングはそのまま大学の実力を反映するものではありませんが、国の高等教育レベルや研究成果の指標として、判断することができます。中国が20世紀90年代に大学併合による高等教育の改革と強化、また、この20年間、研究教育予算を年々増加した結果、この成果が表れてきたのではないでしょうか。
ラッキープリント スタッフ一同
新たな船出
本日99代目の菅義偉首相が誕生しました。菅内閣も今晩発足する予定です。日米、日中、日露、日韓などいろいろな外交上の課題もありますが、コロナ禍の中に、大型財政出動によって、企業の出血を一時的に止められたものの、病の体から健康体へと経済の立て直しをこれからどう進めていくのかは、菅新政府の真価を問われます。
菅首相主導の改革はどういう方向性を示し、社会全般や企業、個人にどういう影響を与えるのでしょうか。状況の好転を祈りながら、期待も膨らみます。
ラッキープリント スタッフ一同
さらば、アンドロイド
アメリカ政府が中国の通信機器大手企業、華為技術(ファーウェイ)に米グーグルのOS「アンドロイド」やIC部品供給などの制裁強化を乗り出し、ファーウェイのスマホ生産継続が危ぶまれている中、消費者事業部のCEO余承東(リチャード・ユー)は昨日9月10日に、アメリア技術をに基づかず、「リナックス」をベースに開発した自社OS鴻蒙(ホンモン)を12月発売のスマホに搭載させると発表しました。
鴻蒙(ホンモン)はスマホに先立って、すでにファーウェイ製品のテレビ、パソコン、タブレット、電気自動車などの端末に採用しており、独自のHMSシステムも徐々に認知されています。「ホンモン」も「アンドロイド」と同様、オープンソースになっていますが、「アンドロイド」よりも5GでIOT(物と物のインタネット)向けに設計されているのが特徴です。HMSは160万の開発者が登録され、8万以上のAPPを運用しています。4億以上のユーザーを有するそうです。まだ、グーグルのGMSほどではないですが、追い上げが激しいです。
ファーウェイがけして米国の圧力を屈さず、アメリカ技術を頼らない自社製品の生態圏を構築していくことになるでしょう。スマホ分野において、アップル、グーグル以外の第三極になるかどうかは、開発搭載する製品の多さにかかっていますが、国際市場はともかく、14億の中国単一市場の規模を考えると、実現する可能性は十分あるのではないでしょうか。
数年後はエベレスト征服中の勇者がキャンプ地に休憩のひと時、東京にある自宅の家電製品をファーウェイの5Gスマホでコントロールすることが夢ではないかもしれません。なぜなら、ファーウェイはエベレストのハ合目まで、前人未到の5G基地局を造ったからです。
ラッキープリント スタッフ一同
冷戦と新冷戦
10数年前に友人とアメリカについて語った際、美術学校の非常勤講師を勤めている友人は「人種のるつぼで、悲惨ですが、人間の未来である」という意見を思い出しました。イデオロギー、宗教背景、貧富格差の異なる移民がアメリカに集まって、人種も違いますが、共同でアメリカを支えて、人種差別や人権問題と格闘しながら、共存共栄を模索していくのがアメリカの姿です。
主要民族、いやむしろ主要人種というべきアングルサクソンは移民国家のアメリカの20%強占めていますが、政治、経済、金融、軍事あらゆる面におきまして、この20%の人口が独立以来のアメリカ合衆国を240年以上支配してきました。近年、アジアからとりわけメキシコや中南米からの移民が増えることによって、白人の仕事が奪われてしまい、嘗ての白人の楽園が崩壊しつつあります。それはアメリカ社会の分断を招いた根本的な理由ではないでしょうか。
そのうえ、利益追求の資本が実体経済に回さず、金融サービスに一極集中をし、製造業も軍事産業や半導体産業のような高付加価値産業に傾斜しています。2019年の軍事費(7318億ドル)は世界の2位から10位まで足した総額(7257億ドル)にも勝ります。中国の国防費増は年々指摘や非難を浴びますが、2019年は2611億ドルで、GDP(国内総生産)はアメリカの68%ぐらいですが、国防費はアメリカの1/3に過ぎません。GDPに占める割合もアメリカの3.4%と比べれば、フランス、オーストラリアのと同じ、1.9%と低く、ロシアの3.9%、韓国の2.7%、インドの2%、サウジアラビアの8%、イスラエルの5.3%の軍事支出を見てみても、国防費を却って抑えられていることが分かります。
その圧倒的な軍事力を誇るアメリカは、第二次世界大戦後、自ら主導して構築してきた国際組織や国際統治システムを無視や離脱し、嘗ての米ソ冷戦対立のように中国の脅威から自国の覇権を維持するあらゆる手段を駆使します。貿易戦争を仕掛けたり、ハイテク企業をいじめたり、自国の国内法で他国の国内事情を計り、制裁をかけたりします。言わば、一強の時代にアメリカの権益が国際協調よりずっと大事だということになります。
国際社会はこのアメリカの傲慢さを感じ、多少の不満も露わにし始めますが、アメリカ的自由民主主義議会政治や資本主義といった価値を確信している以上、嫌でもアメリカに追従することしかできません。
アメリカ政府はファーウェイら中国のハイテク企業を敵とし、なんでも「国家安全」という一点パリで、強引に排除していきます。自分の権限が及ぶ範囲はもちろんのこと、他国の権限まで圧力を加えることで締めあげようとしています。
数年前のエドワード・スノーデン事件で、アメリカは同盟国を含む監視網をグロバル的に構築していることをよく知られるようになりました。中国の通信機器メーカーや中国発のアプリは、中国政府の意向を伺い、世界から情報を吸い取ることは、明確な証拠もなければ、中国政府も世界監視という野望があると思えません。アップルやグーグル、facebook及びTwitterなどのアメリカビック企業に個人情報を献上していますが、中国の企業なら、ダメという発想はどうでしょうか。
今後5G,6Gの時代にAIが主流の発展を導きますが、Iot(物と物のinternet)で、より多くの家電製品や家具にAIが搭載され、例えば寝室にあるベットの温度までもメーカーが把握することになりますが、利便性よりも不便を選び、個人情報を固く守り抜くか、それとも社会主義のメーカーの安価の製品ならだめで、資本主義のメーカーの高価の製品で利便性を味わいます。
そもそも資本主義も社会主義も人類が国民・国家の文明開化時代から模索し、採用や実践してきた2つの統治モデルに過ぎません。完璧な制度が世の中に存在しないわけで、それぞれ良さと悪さがあり、向きと不向きがあるはずです。「俺が正しい」というのがただのワンマン迷信に聞こえますし、この30年間の中国経済が台頭してきたのも、「社会主義市場経済」をうまく導入してからだと思います。一見社会主義は「計画経済」のはずですが、中国は政治体制は社会主義を採用しますが、経済の分野においては、資本主義得意の「市場経済」に転換をさせたのです。制度上の優勢や劣勢を見極め、お互いにいいところを吸収、改良し、制度そのものの完成度を高めたほうがもっと合理的且つあるべき姿なのではないでしょうか。そうでなければ、民主主義も自由主義も安全保障や人権に拉致され、権威主義に陥ることになるだろうと思います。
ラッキープリント スタッフ一同
DJIのモデルの啓発
3年前のお正月に、中国上海の定番観光地「豫園」の土産さんにところどころ日本人観光客の姿が見えますが、大抵ドロンのコナーに集中しています。手頃のおもちゃから本格的な奴まで、購入するのが多かったです。上海おしゃれなスポット「新天地」に回ってみましたが、中国のドロンメーカー「大疆創新」(DJIとして日本にもよく知られています。)のアンテナショップにやはり多くの日本人が集まっています。非軍事の分野においては、ドロンシェアの7割強をDJIが占めています。モノづくり大国の日本の得意分野のはずですが、東芝の白物家電は中国の「美的」へ売却していますし、シャープも台湾の「鴻海グループ」の傘下にあります。国産スマートホンも日本国内の市場しか売れず、エアコンやテレビや冷蔵庫などの家電製品も海外においては存在感が薄いです。
20世紀の70年代、80年代、電化製品と言えば、「日本製」という時代を経験したきた人間にとっては、過去の栄光が華々しかったのですが、現状は寂しく感じます。製造業の発展は常に技術的進歩と画期的な製品開発が伴います。かつてのようにホンダーの「スーパーカブ」、旭ペンタクス「一眼レフカメラ」、東芝の「ノートパソコン」、ソニーの「ウォークマン」、カシオの「電卓」、「デジタルカメラ」、「レンズ付き携帯電話」あっと驚かされた商品が次から次へ登場しました。今の日本は技術の進歩から興奮を感じている人はどのぐらいいるだろう。そもそも製造業に情熱と執着を抱える人間は先輩の世代より大部減っているように思います。
「日本経済新聞社」がDJIのある機種のドロンを分解し、構成部品を調べたところ、230個パーツのうち、8割以上の部品が通用規格品を採用されていますが、高性能で空中撮影も4k画質になっていますし、自動追跡と障害物回避の機能もついています。ソフトの制御が優れていることが分かります。日本メーカーが同様な機能のものを製造すると2倍以上のコストがかかるそうです。
20世紀の80年代は産業構造は閉鎖的で、企業は材料の供給から完成品製造まで垂直管理をしていましたが、90年代以降、産業構造が垂直から水平へと転換を迎えました。各工程の所要材料や部品をいくつかの大手企業が製造し、各メーカーに提供します。メーカーがこの規格部品を使用し、自分の製品を作ります。圧倒的なコストダウンが実現しますが、品質管理はより難しくなりました。その典型的な例は初期のコンピューターのパーツの許容問題です。その問題を解決したのが飛躍的に進歩したソフトのお陰です。90年代後、ソフト開発の目覚ましい発展で、部品の許容問題の多くをソフト制御によって、是正されました。
これからの車産業においてのEV(電動車)開発もそうです。多くの日本メーカーが蓄電池を研究開発していますが、電池というハードにおいてはパナソニックはすごいですが、テスラは既成の蓄電池技術にソフト制御をうまく加えたことで、立派なEV車を売りさばいています。松下はテスラの電池供給者になりました。
新しい技術や画期的な製品の誕生は普通の人が想像できない中で実現されたものなので、研究開発の実を結ぶかどうかは社会の寛容性を問われるかもしれません。
ラッキープリント スタッフ一同
台風とハリケーンが猛威を振るう季節
台風10号、観測史上、未経験の暴風・記録的な大雨や高波、高潮の恐れがあると伝えられていますが、最大瞬間風速85メートルの風、ペットボトルがガラスを当てるとガラスを貫通できるぐらいの風力で、体験したことがありませんが、想像するだけでもぞっとします。
昨年9月千葉県を襲った台風15号は、最大瞬間風速は57.5メートルでしたが、巨大な送電線も倒れ、大規模な停電が余儀なくされ、甚大な被害をもたらしました。台風進路の右側は、台風自体を動かしている風と反時計回りに巻き込む風が、同一方向で合体し、風がより強くなったのが原因だそうです。
例年も同じですが、梅雨明けし、猛烈な暑さを耐えながら、ようやく秋の気配と感じ始めると台風が欠かさず、訪れてきます。アジアは南方の海上で形成した台風が脅威になりますが、同じ時期にメキシコ湾に襲うハリケーンも凄まじです。2005年ルイジアナ州に直撃した「カトリーナー」が1800人の犠牲者を出したのが記憶に新しいです。
数日前にその「カトリーナー」の威力(最大瞬間風速55m/s)をはるかに上回った「ローラ」(最大瞬間風速67m/s)がルイジアナ州に上陸しました。ルイジアナ州とテキサス州が甚大な被害を被りました。それも最大規模の嵐だそうです。
台風10号は、これから九州に接近または上陸すると伝えられています。コロナ禍の災害対策になりますが、被害の減少を祈るばかりです。
観測史上の規模更新を続ける台風とハリケーンが次々量産する季節になります。「ローラ」の次は「ナナ」というハリケーンがやってきますし、10号台風の続きも間違えなく来ると思います。ハリケーンが来るまでにアメリカの巡洋艦、駆逐艦や戦闘機も被害から守るべく、ほかの地域に避難をしました。人間は自然の力の前にいかに微々たるものなのかと改めて、再認識することができます。コロナウイルスにも台風にも人間が勝てないのに、人類は主義やイデオロギーや価値観の論争と制度確信から、目を覚めて、もっと知恵を結集し、気候変動への共同対策や公共衛生対策を講じるべきではないでしょうか。
ラッキープリント スタッフ一同
タピオカの神髄
台湾発だと思いますが、現在若者の間にすっかりお馴染みのタピオカは10年前に台湾や香港、中国大陸にすでに流行っていました。ミルク紅茶の中になんと不思議の玉が入って、太いストローで、そのモチモチ食感の玉を吸いあげるのです。ミルクティーと玉の味が相性よく、程よい甘さを加えて、斬新な味覚だなと当時感じました。「珍珠奶茶」という中国名になっていますが、「珍珠」は真珠のことで、「奶茶」はミルクティーです。まさに天才的なネーミングセンスで、タピオカの様子を描いているのではないでしょうか。所詮「ナタデココ」的な発想だと思いますが、モチモチ感の「真珠」がミルクティーにこの奇妙な組み合わせと遊び心は世を風靡させています。
数年遅れて、日本にも流行り始めて、特に女子中高生の間に飲み物として、定着しています。タピオカの初体験から、10年経ったが、この不思議な食感をもつ「真珠」は一体なんだと調べました。どうやら南米原産のイモ類の一種、「キャッサバ」から加工されたもので、通常は乳白色になりますが、カラメルなどによって着色され、黒いボール状の「凝固物」になり、「タピオカ」が指しているのはまさにその「凝固物」のことです。
黒いボール状の「タピオカ」は見た目は可愛らしく、またプヨプヨとした食感がたまらないですが、意外とカロリーが高いそうです。尿酸値や糖尿病などを気にせず、平気にこの高糖質、高カロリーの飲み物を飲んでしまうことは羨ましい限りです。
ラッキープリント スタッフ一同
けつに火がついています
8月17日に、アメリカ商務省が中国の通信機器メーカーファーウェイに対し、新たな禁止令を出しました。一国の行政力で一民間企業への「制裁」をエスカレートしました。同時にファーウェイが21カ国における38件の子会社に対しても、「管制リスト」に入れました。アメリカはファーウェイへの部品供給の禁止措置として、今年の5月にすでに昨年の25%超の米国技術基準から5%超に引き下げたばかり、すなわち、25%以上の米国技術が含まれる部品提供禁止から、5%超の米国技術が含まれる部品供給禁止に切り替えました。今回は更に5%から0%にと米国企業の部品供給をすべて禁止しました。アメリカのクアルコム、インテルなどのメーカーはもちろんですが、ファーウェイの取引先、韓国のサンムソン、SKグループ傘下のSKハイニックス、台湾の台積電(TSMC)、日本のソニーなどの企業も影響を及ぼします。サンムソンの半導体の20%、SKハイニックスの40%は中国からの収入です。ファーウェイが開発したスマートホンの主力機種P30proの部品供給を見てみると、1631個の部品のの中に869個が日本企業からの提供になり、特に撮影装置の部品供給はソニーです。
ファーウェイ及びその関連会社への部品供給で、米国の技術0.1%以上含まれれば、たとえ米国製のネジが1個含まれていても、だめということになります。自由競争の市場原理はどうなっていることでしょう。ファーウェイはアメリカ抜きでも生きていかなければなりません。14億人の中国市場を依存すれば、死にはしませんが、海外展開は大きな打撃と損失を被ることに間違えないと思います。米国がOS、半導体チップから、ソフト、ハードまであらゆる分野でファーウェイに制裁を加えることになっているからです。
中国政府は未だに米国との関係を配慮し、米国の企業に対して、同等の報復措置をとっていなく、反発もかなり抑制的と言えますが、米国内では「GAFA」(アップル、マイクロソフト、アマゾン、フェースブックの総称)をはじめとする大手企業が52軒すでにトランプ政府に相手を取って、訴訟を起こしています。外国労働者への入境制限への訴えになりますが、トランプのワンマンぶりに不満が続出しているのが分かります。
しかし長期的にみれば脱アメリカ技術の動きは止まらなくなると思います。特に中国国内において、政府主導で各大学、研究機関、技術関連企業を動員し、脱アメリカ半導体サプライチェンの構築に着手しています。3年から5年、技術開発の進歩によって、部品供給の「自力更生」を期待できるだけではなく、更なる技術革新も製品レベルアップを実現する可能性があります。
5G技術は社会通信基盤、クラウドテクノロジー,IT及び自動運転など、人類未来の生活に大きく関わるゆえに、ファーウェイの5G分野への技術特許が世界一になったため、米国の技術的優位性がなくなり、強引に一民間企業を競争相手として抑えること自体は「アメリカファスト」の象徴かもしれませんが、この超大国が「けつに火がついている」とも感じます。
ラッキープリント スタッフ一同
もっと「ニッチ」に注目
コロナの影響で、遠出や外食を控える中、仕事はもちろん、人々の生活パターンも大きく変わってきています。この新日常はしばらく続くと思います。ですが、たとえ、コロナが収まっても、元の生活状態に戻れるのでしょうか。一度身についた警戒感やソーシャルディスタンス、また「不要不急」による省略モードが水の泡のようにすぐ消えるのでしょうか。恐らく、この「新たな日常」new normalがある程度確立し、人間の意識の中に定着すると思います。
例えば飲み屋に通わず、飲み屋の経営は大変ですが、飲み屋に足を運ばない代わりにデリバリを依頼します。その飲み屋もデリバリに適した料理やサービスを開発しなければ、売り上げの安定を図れなくなると思います。人々が消費をしないのではなく、消費する様式が変わったのです。いかに時代に順応をし、「新たな日常」において、ビジネスモデルの転換や新商品、新サービスの開発に果敢に臨むのかは正念場になるのではないでしょうか。
市場のニーズがより多様化、細分化していく中、細かなニーズをキャッチし、よりニッチな商品開発やサービスの提供ができるのかどうかは多くの中小零細企業にとって、今後ビジネス展開のポイントになると考えています。
「ニッチ」について、よく使われる「隙間」という意味以外に、「最適な生息場所」いわゆる「適所」という意味もあります。生物が生態系の中で得た、「最適な生息場所」のように、人間も企業も自分の「適所」を見つけて、生かすのが大事ですし、「適所」が見つかったことで、もっとも気持ちのいい生き方もできるのではないかと思います。
ラッキープリント スタッフ一同
「世界500企業」ついに中国が米国を超えました。
先日、世界企業番付の2020年版「Fortune Global 500」が米経済紙「フォーチュン」によって発表されました。驚いたのは、中国企業の数(香港を含む)がアメリカの数を追い越したことです。米国は去年同様121社で、中国企業は124社で、ランキング総数の1/4に迫っています。台湾企業9社も入れると、133社に達しており、1995年ランキング発表以来、初めてのことです。日本は53社、三位になっています。
ランキングの数は経済の強さや堅調さを必ずしも表していないと思いますが、世界経済の構図はここまで変わったと感じることができると同時に、かつて1970年代、1980年代の日系企業の台頭と同様に、中国全体の経済規模がレベルアップをし、一つの指標として、これから中国企業の更なる躍進も予想できるのではないでしょうか。
500企業の売り上げ総額も33兆ドル(3530兆円)にのぼり、ほぼ2019年の米国と中国のGDP(国内総生産)の合計に相当します。ランキングトップは7年連続でアメリカの「ウォルマート」。それに「中国石油化工(シノペック)」、「国家電網」と「中石油(中国石油天然気集団公司)」が続きました。5位、6位にオランダ・イギリスの「ロイヤル・ダッチ・シエル」とサウジアラビアの国有石油会社「サウジアラムコ」がランキングし、7位はドイツの自動車メーカー「フォルクスワーゲン」、8位は「イギリス石油会社」、9位は米国の「アマゾン」、10位は「トヨタ自動車」の順になります。
中国企業の中身を見てみると、依然として銀行、保険、石油電力及び不動産企業が目立ちますが、「山東鋼鉄」、「上海医薬」など新しい顔ぶれも加わっています。2018年から米国の部品供給停止などの制裁を受けている中国通信機器メーカー「ファーウェイ」も、凹たらず、中国市場にスマートフォンのシェアが伸び、脱アメリカ技術のパソコン発売など、去年の61位から49位へと大きく順位が上がっています。10年前からインターネット事業に参入し、今回のランキングにもっとも若い企業「シャオミ(Xiaomi)」も422位に入りました。急成長の背景に中国14億超の膨大市場と積極的な海外展開があると見られます。
1995年、「フォーチュン」誌が初めて「Fortune Global 500」を発表した当初、世界貿易機構(WTO)が成立したばかりで、中国は2社しか登場しませんでしたが、1997年、4社がランキングしました。2001年にWTO加盟を果たし、同年12社がランキングしていました。12~124社への成長は所要時間19年間、同誌によれば、嘗てないスピードだそうです。
急ピーチに経済が巨大化してきた中国とどう付き合うかはアメリカを始めとする西側諸国の課題になります。政治、世論、国際法律、経済、金融、軍事あらゆる手段でこの勢いを止めようとする強引なやり方もありますが、その抑圧の先に何があるのかと予想でき、コントロールできればいいですが、グローバル化が進んで30年あまり、経済活動におきまして、お互いに入り混じっている状況の中にサプライチェーンがうまく構築してきています。
しかし東西冷戦時代を経てきたおじいさんたちが政治主導で「封じ込め」という行動に移そうとまず自分たちの「正統性」を強調し、仲良しグループの結束を呼びかけますよね。「俺のバラ園に百合が許せんぞ」と異物叩きをし、屈服させるのです。どうもガキのレベルと感じてしょうがないのです。
「バラ園に百合が入っても、別に綺麗だし、共存共栄すれば」と逆に思いますし、アヘン戦争以来の屈辱と苦難をいろいろと経験してきた中国も米国の圧力をけして真正面から激突するのではなく、懸命に交わしていくことになるだろうと思います。ボクシングのパンチを「合気道」や「太極拳」で交わすように・・・
ラッキープリント スタッフ一同